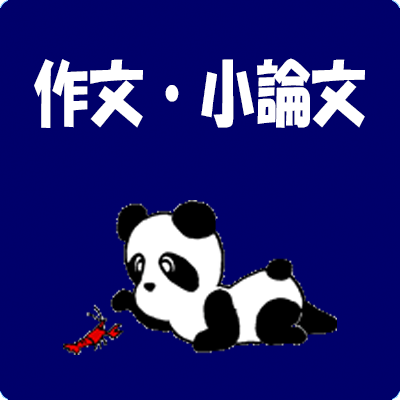パラグラフ・ライティングとは
前ページで、実は一文一文が重要な役割を果たし、文の流れを作っているということが分かったと思います。では、論理的文章で使用される段落(パラグラフ)とは、どのように書かれているのでしょうか?ここでは、最も基本的なパラグラフ・ライティングについてお話しします。
英語に比べ日本語は非論理的言語だ、と言う人がいますが間違っています。地球上に非論理的言語など存在しません。言語が非論理的だったら、コミュニケーションなど取れないからです。
にもかかわらず、日本語が非論理的に感じるのはどういうことでしょうか?
それは、使っている人間の頭の中が非論理的だからです。
英語圏に限らず、海外ではどのように文章が書かれるのでしょうか?それがこれから説明するパラグラフ・ライティングです。海外で守られている書き方を、日本人は非論理的な思考で文章を書いてしまうため、作文が難しく感じてしまうのです。
では見てみましょう。
まず、パラグラフ・ライティングの段落は、基本的に3つの部分で構成されます。それぞれの部分を『中心文』『展開部』『結びの文』と呼びます。
中心文
段落を構成する一文一文には働きがあります。その働きの中で、最も重要な意味を表す文のことを中心文と言います。中心文は、段落の最初に書くのが“きまり”です。ここでことさら“きまり”と書いたのは、これを無視して書く作家が大勢いるからです。支持文/展開部
中心文に対し、中心文の内容を詳しく説明したり、補足説明をしたり、例示したりする文です。いくつもの文を使って、中心文を説明する展開部分にあたります。結びの文
第二の中心文です。最初に中心文を書き、展開部でその中心文の内容を書き、最後にまとめる形に仕上げます。以上の3つの部分で段落が構成されています。これがパラグラフ・ライティングです。
では、具体的に見てみましょう。
例文①
|
中学生は携帯電話を持つべきではない。インターネットや携帯電話を通じて、未成年者が犯罪に巻き込まれるケースは増加の一途をたどり、また、非行や学業不振の遠因にもなっているからである。さまざまな情報を携帯電話を通じて手軽に入手できる現在の情報化社会は、便利さが増す一方で、無防備な子どもたちを有害情報にさらす結果となっている。携帯電話を巡る未成年者の問題行動は、出会い系サイトの利用、無計画な電話利用による浪費、授業中のメール交換等学習面への障害、また、犯罪や暴力行為のための連絡等、多岐にわたっている。新聞報道によると、非行中学生の携帯電話所有率は6割強とも、7割強ともいわれ、彼らの携帯電話への強い依存傾向が指摘されている。中学生の携帯電話所有は、百害あって一利なしといえよう。 |
赤字部分が始まりの中心文です。中心文で筆者が主張し、黒字部分の支持文、展開部ではその根拠を書いています。そして、最後の緑字の結びの文で主張を再確認しています。
この段落(パラグラフ)は、全部で6つの文(下の①~⑥)で構成されています。1つの中心文(①)、4つの支持文(②~⑤)、そして、1つの結び文(⑥中心文)です。
① 中学生は携帯電話を持つべきではない。 (書き出しの中心文です)
↓次に支持文が続きます。
② インターネットや携帯電話を通じて、未成年者が犯罪に巻き込まれるケースは増加の一途をたどり、また、非行や学業不振の遠因にもなっているからである。
↓次の支持文へ流れます。
③ さまざまな情報を携帯電話を通じて手軽に入手できる現在の情報化社会は、便利さが増す一方で、無防備な子どもたちを有害情報にさらす結果となっている。
↓次の支持文へ流れます。
④ 携帯電話を巡る未成年者の問題行動は、出会い系サイトの利用、無計画な電話利用による浪費、授業中のメール交換等学習面への障害、また、犯罪や暴力行為のための連絡等、多岐にわたっている。
↓次の支持文へ流れます。
⑤ 新聞報道によると、非行中学生の携帯電話所有率は6割強とも、7割強ともいわれ、彼らの携帯電話への強い依存傾向が指摘されている。
↓最後の結びの文でまとめます。
⑥ 中学生の携帯電話所有は、百害あって一利なしといえよう。 (結びの中心文です)
これが段落の流れ、構成です。そして、この段落の①と⑥の文を合わせると、
|
中学生は携帯電話を持つべきではない。中学生の携帯電話所有は、百害あって一利なしといえよう。 |
となります。これを綺麗な文にまとめたものを『要約』と言います。
例文②
|
東海道新幹線の開通以来、新幹線は、日本の交通の大動脈として重要性を増し続ける一方で、単なるスピード重視から脱却しようとしている。1964年の開業当時世界一の営業速度を誇ったひかりは、最高時速210㎞で東京―新大阪間を4時間で結んだ。東京オリンピック、大阪万博を経て、1972年には山陽新幹線岡山が、続いて1975年には山陽新幹線博多が開業している。1986年、東海道、山陽新幹線が時速220㎞で運転を開始、東京―新大阪間は2時間56分と大幅に短縮された。さらに、1992年には、のぞみの登場により、最高時速270㎞、東京―新大阪間は2時間30分までに縮まった。1999年春には、乗車時の快適性を高速化より優先したのぞみの新型車両が登場した。このように、新幹線は、高速化のみならず、快適さを追求する姿勢を強めてきている。この時点で、JR各社の長年にわたる新幹線高速化への動きは1つの節目を迎えた。 |
上に同じく、赤字部分が中心文にあたります。そして、黒字部分の展開部では、お話しが時系列で続き、最後の緑字の部分が結びの文になっています。
この段落(パラグラフ)も例文①のように分解してみましょう。この段落は全部で7つの文(下の①~⑦)で構成されています。1つの中心文(①)、4つの支持文(②~⑥)、そして、1つの結び文(⑦)です。
① 東海道新幹線の開通以来、新幹線は、日本の交通の大動脈として重要性を増し続ける一方で、単なるスピード重視から脱却しようとしている。 (書き出しの中心文です)
↓次に支持文が続きます。
② 1964年の開業当時世界一の営業速度を誇ったひかりは、最高時速210㎞で東京―新大阪間を4時間で結んだ。
↓次の支持文へ時系列で流れます。
③ 東京オリンピック、大阪万博を経て、1972年には山陽新幹線岡山が、続いて1975年には山陽新幹線博多が開業している。
↓次の支持文へ時系列で流れます。
④ 1986年、東海道、山陽新幹線が時速220㎞で運転を開始、東京―新大阪間は2時間56分と大幅に短縮された。
↓次の支持文へ時系列で流れます。
⑤ さらに、1992年には、のぞみの登場により、最高時速270㎞、東京―新大阪間は2時間30分までに縮まった。
↓次の支持文へ時系列で流れます。
⑥ 1999年春には、乗車時の快適性を高速化より優先したのぞみの新型車両が登場した。
↓最後の結びの文でまとめます。
⑦ このように、新幹線は、高速化のみならず、快適さを追求する姿勢を強めてきている。この時点で、JR各社の長年にわたる新幹線高速化への動きは1つの節目を迎えた。 (結びの中心文です)
そして、この段落も例文①のように①と⑦の文を合わせると、
|
東海道新幹線の開通以来、新幹線は、日本の交通の大動脈として重要性を増し続ける一方で、単なるスピード重視から脱却しようとしている。(このように、)新幹線は、高速化のみならず、快適さを追求する姿勢を強めてきている。この時点で、JR各社の長年にわたる新幹線高速化への動きは1つの節目を迎えた。 |
となります。『要約』です。
いかがですか?
これがパラグラフ・ライティングです。
それぞれの段落とは、このように書いていくものなのです!!
『文章は必ず段落分けしなさい!』
こんな指導を受けたことはありませんか?けど、その段落の中身については詳しく教えてくれないもんだから、何となく段落分けしていた、それが現実ではありませんか?
しかし、このパラグラフ・ライティングを知った後ではどうですか?今まで適当に書いていたことが恥ずかしくなってくると思います。
思いついたことを思いついたままに書くのは論理的文章とは言いません。書く前にしっかりと段落の数と構成を考え、段落内のこの3つの部分にあたる内容をじっくりと考えた上で書き始めるのです。
さらに!
ここまで来ると、あることに気がつきませんか?
そうです。国語の現代文試験、論説文(説明的文章)が出題されたら、注意して見てみましょう。設問のほとんどが中心文から出題されています。段落の中心文に傍線が引かれていて、そこから問題が出題されています。
|
鉄 則 パラグラフ・ライティングこそ、論理的文章の大原則! |
小論文が書けるということは、読解力向上にも大いに役立つわけです。なぜなら、現代文で出題される文章の著者と同じように文章を書こうとするからです。